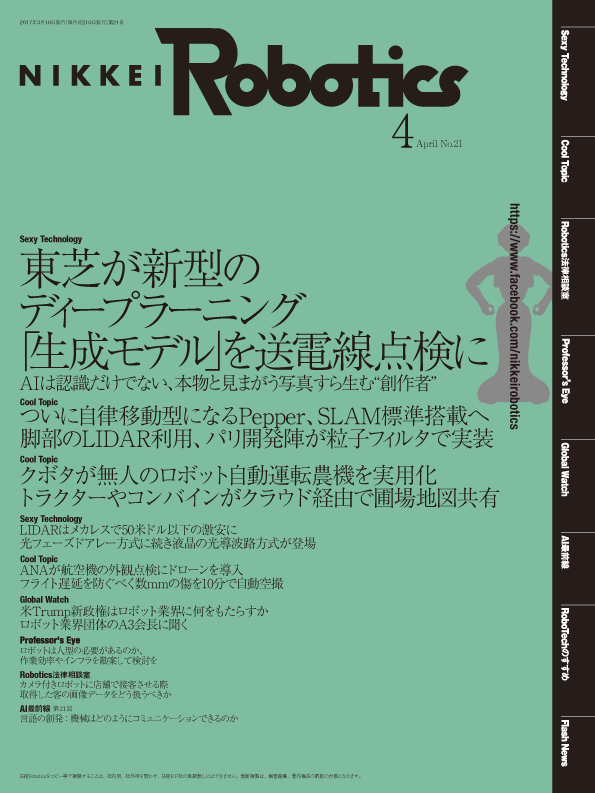『日経Robotics デジタル版(電子版)』のサービス開始を記念して、特別に誰でも閲覧できるようにしています。
有人航空機とのニアミス問題からドローンを厄介者として見ることの多かった航空業界が、ドローンの積極活用に乗り出した。
先手を打ったのは、全日本空輸(ANA)だ。フライト前の整備点検時に、ドローンで航空機の外観検査をする。航空機の上部を約10分間自動飛行させ、写真を撮影。高所作業車に乗って人が目視検査せずとも、破損箇所がないかなどを即座に確認できるようにした。
特に確認するのは、落雷による損傷箇所だ。飛行中に落雷があった場合、次のフライトまでの30分余りの間に損傷箇所を見つけ出す必要がある。ここにドローンを使うことにした。従来は専門資格を持った整備士が高所作業車に乗り、航空機の周りを1周しながら目視で確認していた。長い時は1時間かかる場合もあり、フライトの遅延などにつながることもあった。
2017年2月14日、大阪国際空港(伊丹空港)に隣接するANAのグループ会社のMRO Japanの格納庫前で、ボーイング787-8をドローンで試験点検した(図1)。ドローンの自律飛行サービスを手掛けるソニー系ベンチャーのエアロセンスと共同で実施した。2018年以降にまずは、落雷に遭う頻度の高い日本海側に位置する山形県の庄内空港で実運用する考えだ。
ドローン事業推進の組織を新設
ドローンが登場して以来、有人機との接触問題は常に議論に上ってきた。実際、航空機とドローンの接触事故は英国のHeathrow空港やフランスのCharles-de-Gaulle空港など海外で数多く報告されている。米連邦航空局(FAA)によれば、2016年には米国内だけで1200件以上のニアミスが発生したという。
日本では今のところ致命的な事故につながったケースはないが、何よりも安全を重視する航空会社が神経質になるのは当然と言える。
そうした航空業界にあって、ANAは、ドローンの利活用に積極的な企業だ。同社は中核である旅客事業以外の新規事業の1つにドローン事業を据える。2016年4月には新規事業の推進に向けた組織「デジタルデザインラボ」を設立している。「旅客機で培ったノウハウを生かし、ドローン産業に貢献したい。2018年には事業化し業務効率化を目指す」(同社 デジタルデザインラボ チーフディレクターの津田佳明氏)。
津田氏は、ドローンの運行管理システムの環境整備を目指す産学官組織「JUTM」(日本無人機運行管理コンソーシアム)の幹事も務める。東京大学や熊本県天草市とは、災害時の緊急用のヘリコプターとドローンとの衝突防止策などを検討してきた。今回、こうした知見を生かし、航空機の点検という自社の業務プロセスの改革にドローンを生かした。
遅延を左右する点検を簡便に
航空機の整備点検は、頻度などに応じて数種類あるが、今回は着陸から次のフライトまでの間に搭乗ゲート周辺の駐機場で行う「ライン整備」と呼ばれる点検にドローンを適用した(図2)。
ライン整備では整備士が航空機の周囲を見て回り、タイヤの破損がないかなど複数項目の点検を行う。さらに飛行中に落雷があった場合は、破損の箇所や程度を確認する「特別点検」が加わる。雲の中に入った際などに航空機が被雷すると、パイロットは閃光から落雷があったことを認識できるが、どの辺りに被雷したかまでは分からない。このため、着陸後の整備点検で場所を特定する必要がある。整備士が高所作業車を使って3人体制で見て回る必要があり、人手と時間がかかる上、危険の伴う作業だった。
ANAグループの機体の整備を請け負うMRO Japanによれば、2015~2016年冬の半年間で航空機への落雷は、120件。平均すると3日に1度被雷している計算だ。