しかし間もなく,かつてない難問に直面する。光学ズームの倍率が大きくなり,補正範囲の不足が顕在化したのである。何しろ当初は6倍だった倍率が瞬く間に10倍になり,20倍に手が届きそうになっていた。倍率が大きくなると,わずかな手ブレが大きな画面ブレを引き起こす。既存の電子式の手ブレ補正技術では,もはや対処できなくなる。日下に求められたのは,その抜本的な解決であった。

中山は,物腰が柔らかで雰囲気も大らか。しかし技術者としての経験は長く,技術を目利きする眼孔は鋭い。おまけに根っからのカメラ好き。その知識量は半端じゃない。優しい口振りながら厳しい指摘をする中山に,日下は歯切れのいい返事ができず,ただただもどかしさを感じていた。
光学式への思いが募る
「うーん。電子式はいつまで通用するんやろ」
中山と議論を交わし,その指摘を反芻はんすうするうちに,日下は電子式の手ブレ補正の限界をひしひしと実感する。補正範囲の不足を補おうとすると,再びコストや解像度の問題が起きる。一体どうすればいいんだろう…。
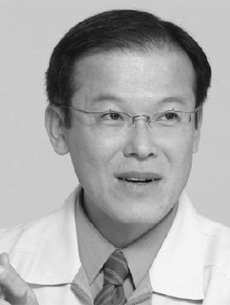
解決策がなかったわけではない。光学式の手ブレ補正技術の採用だ。光学部品で手ブレを補正すれば,補正のための画像メモリも,解像度の低下も発生しない。しかしブレンビーの成功体験も手伝って,社内には「手ブレ補正といえば電子式」という確固たる認識が出来上がっていた。おまけに日下は,電子式の開発を突き詰めてきた張本人。自らが電子式の手ブレ補正の限界を認め,その進化を止めてしまっていいのだろうか。

長い間,考えに浸りがちだった頭をもたげ,日下はあたりを見渡してみる。冷静になると,光学式の手ブレ補正技術を採用する他メーカーもあるではないか。さらに過去を振り返ると,1988年に光学式の手ブレ補正技術を最初に実用化したのは,ほかでもない松下電器産業である。簡単ではないだろうが,我々が光学式を検討しなくてどうする――。日下の胸の内で,そんな考えが次第に大きくなってくる。
3人の知恵を結集
「林さん,どこから手を着けたらいいいですかね?」

「まずは目標仕様を検討するところから始めますか」
1995年秋。ついに松下電器産業は光学式の手ブレ補正技術の検討を開始する。ワーキング・グループを結成,そこで顔を合わせたのが日下と林孝行,そして山田克の3人だ。
光学式の手ブレ補正技術は,電子式以上に複数の分野にわたる知見が必要になる。だからこそ,まさに補完関係にあるこの3人が集まった。カメラのレンズ鏡筒の設計に詳しい林。レンズなど光学設計に従事する山田。そして制御技術の日下。所属部署や上司は異なるが「小型で高性能の光学式の手ブレ補正技術」という共通の目標を胸に集結する。
ワーキング・グループにおいて重しとなったのが林である。日下や山田にとって,光学式の手ブレ補正技術は未知の領域。どこから着手すればいいのか,さっぱり分からない。対する林は1980年代後半,鏡筒補正方式と呼ぶ光学式の開発をまさに担当していた。ブレンビーの登場とともに電子式が主流となり,いったんはその開発から遠ざかる。しかし当時の経験を請われ今回,参画するのである。
小柄な林だが,その行動力は人の2倍も3倍もある。技術開発に対するねばり強さも誰にも負けない。あまつさえ林には,かつて光学式の開発に携わっていた経験やノウハウがある。林を軸に議論が展開していくのは自然の成り行きだった。
―― 次回へ続く ――



















































