自動車メーカーや国土交通省などが次世代の安全技術「インフラ協調型システム」の開発を進めている。これまでの予防安全技術は,クルマに搭載したカメラやレーダなどを活用する自律型システムだった。このため,クルマから見える範囲の障害物しか検知できず,交通事故を防ぐには限界があった。次世代技術では,通信を活用することでカーブの先の障害物など見えない範囲の障害物を検知することも可能になる。
次世代の安全技術であるインフラ協調型システムは,クルマと道路が通信する「路車間通信」を使うものとクルマ同士が通信する「車車間通信」を使うものに分かれる。それぞれ,通信相手が異なるという以外に,実用化の容易さなどの点で違いがある(表1)。
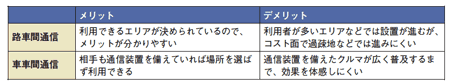
表1●インフラ協調型システム
路車間通信は利用エリアが分かりやすいため普及しやすい。車車間通信は普及には時間がかかると見られている。
路車間通信は,ETCやVICSなど既存のインフラを使って実用化できることから,まずは簡易なシステムを実用化する検討が始まっている。利用できる場所が明示してありさえすれば,ドライバーがサービスを受けやすいというメリットがある。その半面,コストの制約から全国隅々までの普及は難しい。サービス提供エリアは,クルマが集まるところや事故の比率が高い場所に限定されるだろう。
一方の車車間通信は,大都市かそれ以外かを問わず利用できるというメリットがある。ただし,対応車が増えるまでの間は,いつどこで利用できるか分からないという制約がある。たとえ普及率が10%になったとしても,クルマとクルマがすれ違う場合,車車間通信が機能する確率は10%×10%で100回に1回の確率となる。普及率がかなり上がらないとメリットを体感できないため,なかなか普及率が上がらないというジレンマに陥る可能性がある。
このため自動車メーカーは,まず光ビーコンやETCなどの既存インフラを利用した路車間通信型のシステムの実用化に向けて動き出している。
車車間通信は2010年以降
実用化が段階的に進む路車間通信に対して,車車間通信は2010年ごろからようやく導入が始まる見込みだ。
実用化に向けての道のりは長いが,国土交通省は2005年10月に車車間通信の実証実験を公開した。車車間通信にどの周波数を割り当てるかはまだ決まっていないため,今回の実験では暫定的に5.8GHz帯を使った。5.8GHz帯はETCも使っているが,ETCが使用していないチャンネルを車車間通信用に割り当てたという。
トヨタ自動車は,カーナビに内蔵している3次元地図の表示に,車車間通信で得た警報表示を組み合わせた。同社がこだわったのは,多くの車両が連なっている場合の音声案内。交差点での右折時などに単にクルマがきているかどうかという情報にとどまらず,クルマの影に隠れてバイクがいるかどうかなど,より実際の状況に近い情報をドライバーに伝えるよう意識したという。
ホンダは,障害物に接近すると自動的にブレーキをかけるほか,ステアリングやアクセル・ペダルなどを振動させてドライバーに注意を促すシステムとした。音や表示は運転歴の浅い人や長い人で応答時間に差がある。体感警報であれば運転経験に関係なく危険を認識できる,という考え方である。
日産自動車は,交差点で出会い頭や右折時の衝突事故が起こりやすい時に,ドライバーが交差点手前でいったんかけたブレーキを離して再度進もうとすると警報する仕組みを導入した(図1)。

図1●日産自動車の車者間通信の実証実験
















































