オシロスコープは,時間波形,すなわちタイムドメインにおける信号の測定・解析ツールである。単一の信号波形を測定することも多いが,信号と時間という意味では複数の信号間の関係を知りたいことの方がむしろ多いかもしれない。オシロスコープで同時に複数の信号を扱えるようになれば初級エンジニアは卒業だ。
最近のオシロスコープは4チャネルを基本とし,1および2チャネルモデルをバリエーションとして揃えるものが多くなった。デジタル回路などを扱う場合,どうしても多チャネルを同時に見たくなる。こうした場合4チャネル機だと都合が良い。
パラレルポートの動作を詳細に検討する場合などは,ロジック・アナライザのようなより多チャネル化が必要と考えるかもしれないが,オシロスコープでは波形の詳細な部分を観測することになるため,画面に同時表示させ,それぞれを分かりやすく識別できる信号の数は4つが限度である。
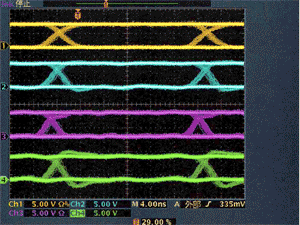
図1:4チャネルのデジタル信号のアイパターン
<図1は>4チャネルのデジタル信号のアイパターンを表示した例である。カラー表示のおかげで4つの信号を明確に識別できるが,同時表示での波形観測という意味で4つが限度というのが納得できるだろう。
実際,R&Dや製造・サービスなどの現場において,頻繁に利用するのは1チャネルと2チャネルだ。複数信号の測定技術という意味では2チャネルをマスターすれば後は応用が利く。ここでは,電源回路を例に2チャネル測定のポイントを探る。
<図2>および<図3>はスイッチング電源の典型的な測定例である。
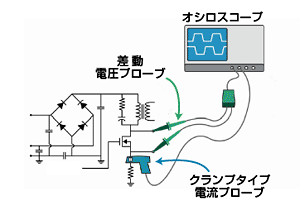
図2:スイッチングデバイスの損失測定(機器接続)
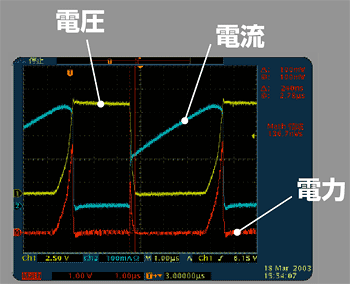
図3:スイッチングデバイスの損失測定(測定例)
スイッチングデバイスであるパワーMOS FETの動的な損失(消費電力)を測定するため,ソース-ドレイン間の電圧とドレイン電流を検出する。
二つの波形を眺めるだけでも十分な価値があるが,オシロスコープの演算機能を使って両者の積を演算した波形を同時に描くことでスイッチのオン・オフで発生する瞬時的な電力損失のダイナミックな変化を知ることができる。
電圧と電流の比(商)を演算すれば,FETのオン抵抗も分かる。
さて,この場合のポイントを幾つか挙げてみよう。
第一のポイントは信号の検出法とプローブの選択だ。<図2>で明らかなように,スイッチ素子はACラインと直結したいわゆる一次側にある。したがってオシロスコープや測定者とはグラウンドの基準点が異なる上,その間に高い電圧がかかる。
そのため,何らかの形で被測定回路とオシロスコープ間を絶縁しなければならない。測定ポイントをアイソレーションアンプに導いた後にオシロスコープに接続することも考えられるが,やや大がかりになる。
電圧と電流二つの検出という点だけで見ても,電圧については,プローブを当てる検出点(FETのソースとドレイン)がグラウンドから浮いており,スイッチングの際のコモンモード電圧がかかる点が問題になる。2本のプローブを使ってソースとドレイン電圧を個別に測定しチャネル間の差を求める方法もあるが,CMRR(同相信号除去比,common mode rejection ratio)やダイナミックレンジの点からベストとは言えない。
電流検出では何らかの方法で電流を電圧に変換しなければならない。ソース(またはドレイン)側の抵抗の電圧降下(図ではソース電圧)で代用することも可能だが高速のスイッチングでは浮遊容量などを通じて電流が流れるので必ずしもFETの電流を反映しない。
電流検出用に低抵抗値のシャントを入れる方法もある。その場合はシャントの片方がグラウンドにできる回路に限定されることのほかに,シャントのインダクタンス分が回路動作に及ぼす影響を考慮する必要がある。単線のインダクタンスは,おおよそ1cmあたり10nHある。長さ1cmで10mΩのシャントだとしてもその時定数は1μsにもなり,高速スイッチングに対して無視できない。
結論として,電圧の検出には差動プローブを,電流検出にはクランプタイプの電流プローブを使うのが好ましい。
ただし,その場合も差動プローブは一次電圧に耐える高耐圧なものである必要がある。高速デジタル信号用の差動プローブなどは一般に低耐圧なので注意したい。
同様に電流プローブは単純なCT(電流トランス)ではなく,直流も測定可能なタイプでなければならない。電圧電流共にスイッチング波形の持つ周波数帯域を満足したものでなければならないのは当然である。
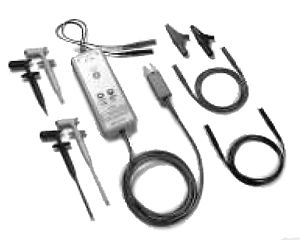
図4:高電圧差動プローブの例
テクトロニクス TCP0030型
DC~120MHz 最大実効値電流:30A

図5:AC/DC電流プローブの例
テクトロニクス P5205型
DC~100MHz 耐圧:1300V
ここまで,パワー測定における第一のポイントを述べてきた。次のポイントは,チャネル間のスキュー(skew:時間的なズレ)に伴う誤差の対策だ。
デバイスのスイッチング損失は,オン・オフのトランジェントにおいてデバイスが完全オンまたは完全オフの飽和領域からリニア領域を横切って他方の飽和領域に遷移するときのわずかな期間に発生する。
理想的には電圧ゼロでオンまたは電流ゼロでオフしているわけだが,電流もしくは電圧の切り替えタイミングがずれると双方の値が有限となって,(両者の積である)損失が発生する。オシロスコープでは,この微妙なタイミングのズレや双方の遷移波形を測定するわけである。
ところが,測定ポイントからオシロスコープの入力端に信号を導くまでの間,あるいは変換する段階でチャネル間に遅延時間の差が生じ,あたかも測定信号が元々時間差を持っているかのように測定されてしまうことがある。これがスキュー誤差だ。
<図6>は実際には電流と電圧が同時に立ち下がる信号を観測したものだが,あたかも時間差があるかのように測定されている。この状態でスイッチングデバイスのパワー測定をすると大幅な誤差を生じてしまうことになる。
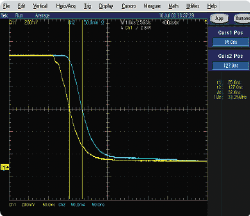
図6:スキューを含んだ測定信号
実際は同時性のある2信号があたかも時間差があるかのように測定されている
そこで,測定開始前に測定系のスキューをゼロに合わせ込む作業が必要になる。これをデスキュー(de-skew)と呼ぶ。
オシロスコープがデジタル化されたことでデスキューはアナログ時代と比べ簡単になった。補正する量さえ分かればデータの時間位置を変えるだけで済むからである。指定されたプローブを使うと,プローブごとに書き込まれた遅延時間を内部で自動補正してくれるオシロスコープもある。また,同時性が明らかな信号を入力してボタンを押すとズレが補正されるデスキュー機能を持ったオシロスコープやソフトウエアもある。
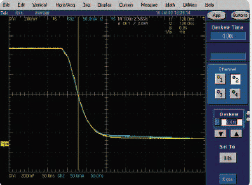
図7:デスキューによって補正された2信号
<図7>は<図6>で生じたスキューをデスキュー機能によって補正した結果である。二つの信号がきれいに一致している。
なお,デスキュー用に<図8>のような治具も供給されている。
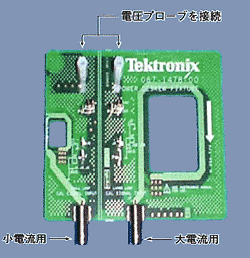
図8:デスキュー用測定治具の例
スキューに類似したパワー測定の注意点としては,オフセットと測定のダイナミックレンジがある。
例えば電流プローブでDCオフセットが発生すると,オフの時にも電流が流れているように測定されてしまう。したがって測定に当たってはプローブのオフセット補正(ゼロバランス調整)をしっかりすることが大切だ。
また,オン抵抗などを測定する場合はFETがオンしている時点でのわずかな電圧を測定することになるが,一方でオフ時の電圧が大きいためオン時の電圧を正確に測定できるダイナミックレンジと分解能が得られないことがある。
そこで,測定レンジを上げたくなるのだが,オフ時の電圧によってプローブやオシロスコープの内部回路が飽和(オーバードライブ)してしまうと,オンに戻っても回復に若干の時間を要する。したがってオンした直後の波形を観測する際には注意したい。
パワー測定の第三のポイントはX-Y表示モードの利用である。
スイッチング電源は様々な動作モードを持ちダイナミックな動きをしている。通常は他の信号解析と同様に横軸を時間にとって測定するが,動作の全体像を見極めることは意外に難しい。
例えば<図9>は電源を立ち上げた際の電圧と電流波形を通常のスタイルで表示させたものである。同図から電圧と電流が定常に至るまでどのように変化するかが分かる。
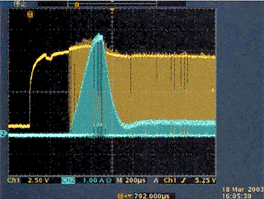
図9:立ち上げ時の電圧と電流波形
(2チャネル通常表示 横軸:時間)
しかしながら,図9から例えば立ち上げのトランジェントでFETのSOA(安全動作領域:Safety Operation Area または Area of Safety-operation:ASO)を超えているか否かを判断するのは難しい。
こうした場合,電圧と電流をX軸Y軸に採った表示をさせると全体がスッキリする。<図10>は<図9>の信号をX-Y表示させたものだ。SOAに対して電圧と電流がどのような軌跡を描くかがひと目で分かる。
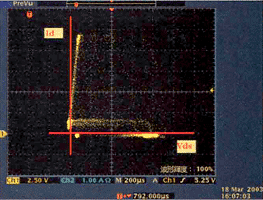
図10:電源立ち上げ時の電圧と電流波形
(X-YによるSOA表示)
同様に<図11>と<図12>は電源の負荷が変動した際の挙動を通常の表示とX-YによるSOAの表示とで見比べたものである。回路としての動作を見極めるには通常表示が欠かせないが,デバイスのストレスに対する余裕度はX-Y表示にしたほうが断然把握しやすい。
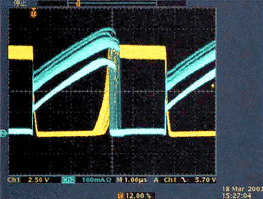
図11:負荷変動時の電圧と電流波形
(通常表示)
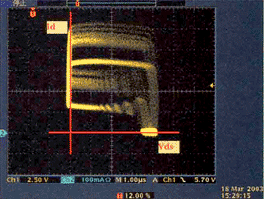
図12:負荷変動時の電圧と電流波形
(X-YによるSOA表示)
ちなみに,オシロスコープを使ったX-Y表示は一般にリサージュ(Lissajous:人名)と呼ばれ,2信号の周波数比を見る際などに使われてきたが,アナログのオシロスコープの場合は縦軸と(Y)と横軸(X)の周波数特性に大きな差があったため高速信号には適用できなかった。
デジタルオシロスコープではそのような制限は原理的に無いので,電源以外でも,もっと多用されても良い手法である。
パワー測定の最後のポイントは,電源測定専用ソフトウエアの併用だ。
スイッチング電源は,スイッチデバイスだけでなくトランスやインダクタ,コンデンサなどが複雑に関係し合って動作する。それらの部品や回路動作の解析が必要な場合,オシロスコープ単体では解析操作が面倒な部分も出てくる。
例えば,インダクタのインダクタンスやB-Hカーブはインダクタを流れる電流と両端の電圧から求めることができる。しかしながら,それには電圧データの積分処理が必要になる。
オシロスコープでの電源解析専用ソフトには,そうした積分処理機能などがあらかじめ搭載されている。
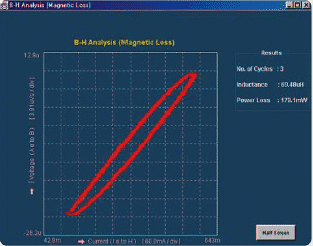
図13:インダクタのB-Hカーブ
(電源実稼働状態の特性が得られる)
<図13>はインダクタの専用ソフトでB-Hカーブを求めたものである。BHアナライザなどを使った部品単体の静的な測定と異なり,動作中のインダクタ電圧と電流から求めたものなので,実際の使用条件下における特性が得られるメリットがある。
<図14>には同様のソフトウエアを使って蛍光灯用電子安定器のSOA解析をした例を示す。
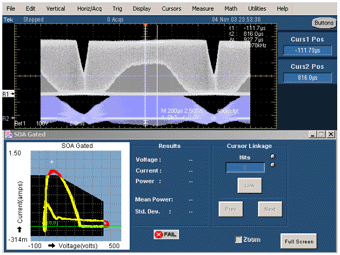
図14:蛍光灯用電子安定器のSOA解析例



















































