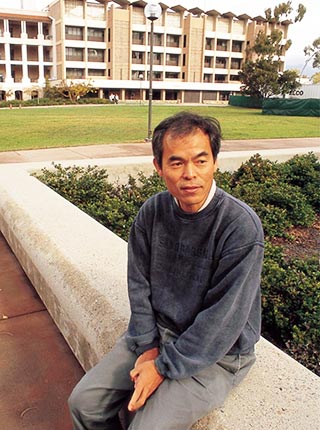
(写真:栗原克己)
――20年間勤めた日亜化学工業を退職し,University of California Santa Barbara校の教授に転身してから1年がたちました。この間に最も変わったことは何ですか。
中村氏 日亜化学工業時代に比べて3倍くらい忙しくなりましたね。会社を辞める直前は,自分は直接研究にタッチできずに,机の前でぼけっとしている毎日でした。研究に関する指示は,私を素通りして上司から部下に伝えられていましたから。米国に移ってからは早いときで朝6時半にはオフィスに来て,夜10時くらいまでずっと働いています。休日も仕事。ゆっくりする暇はありません。
――中村さんは,技術者がやり遂げた仕事の成果を正しく評価できない日本のシステムに限界を感じて,渡米を決意しました。そのときといまとでは,日本に対する印象は変わりましたか。
中村氏 ますます日本が自由のない国に見えるようになりました。こっちは仕事を進めるうえで上下関係がまったくない。ともかく能力主義,自由主義なんですよ。学生でも教授でも研究者としては対等です。ところが,日本ではいまだに年功序列が幅を利かせている。しかも肩書で上下関係が決まるでしょ。平社員が社長と直接話をしようと思ったら一大事なのが,それを象徴しています。
――会社の研究員と大学の教授では,仕事のやり方はだいぶ変わりましたか。
中村氏 ある現象の背景にある理論を,より深く勉強しなければならなくなりました。会社にいたころは,理論は後回しでもともかくモノを作ればよかったんですけどね。大学ではそうはいかない。自分が理論を根本から理解しないと,学生に教えられませんから。博士課程の学生7,8人を相手に,今年の1月から毎週2回,90分の講義を始めたんですけど,そりゃもう毎回準備で大変です。講義を始める前は本当に自分に務まるかどうか,それはそれは心配で…。いままで講義なんてしたことなかったですし,あらたまって人に何かを教えることも大嫌いでしたから。でも実際に講義を始めてみると,実は自分自身の勉強になることがわかりました。
――学生とのやりとりから得るものが多いんですね。
中村氏 こっちの学生は宿題を出すと,私が悩むくらい難解な答えを出してくる。内容によっては,私より学生の方が詳しく知っていることもある。自分が学生だったころを思い出すと大違い。もうたじたじですよ。だから教える側としても負けずに勉強しないといけない。学生を追い越そうと,こっちも必死になる。これで自分が進歩するわけです。これほど学生の質が高いのは,なぜ博士課程で学ぶのかという目的意識をしっかりもっているからでしょうね。研究助手のために5人の学生を雇ったんですが,そのほとんどは学部を卒業して私に会いに来たときから「GaN(窒化ガリウム)のバルク基板を作る技術を開発して,ベンチャー企業を興したい」なんてはっきり言う。こちらでは自分の学力に自信のある学生ほど独立心が強い。博士課程に入る前は「大学に残って先生になりたい」と言っていた学生も,卒業するころにはほとんどが独立志向に変わるそうです。だから,優れた学生を採るときには,将来会社を興す意志があるかどうかで判断するほどです。「大企業に就職したい」なんていう学生はちょっとね。




















































