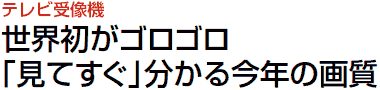画面寸法が65インチ型,色再現範囲がNTSC比105%,暗所コントラスト比が8600対1…。今年のCEATEC会場には「世界最大」や「世界最高」といった分かりやすい特徴を前面に出したテレビがズラリと並んだ。いずれの項目も,見た目の「臨場感」や「美しさ」に欠かせない重要な数値であり,ひと目で分かるその違いを強くアピールした。
その決め手になったのは,パネルやバックライトなどの新しいディスプレイ部品の実用化である。中でも,キヤノンと東芝が共同開発を進めるSEDテレビの周りには,全く新しいパネルを搭載したテレビの登場ということもあり幾重もの人垣ができた。液晶/PDPも含めて,大画面テレビに映す映像の迫力や美しさが今後数年でガラリと変わることが見て取れた。
世界最大の称号を奪還
画面寸法でいえば,シャープが展示した65インチ型が液晶テレビの中でもずばぬけていた(図1)。2004年10月5日,朝10時にCEATECが始まったと同時に,同社はこの液晶テレビの発表会を展示ブースで催した。65インチ型の液晶テレビの開発成功で「これまで40インチ型以下が液晶,それ以上がPDPといわれたすみ分けがなくなる」(同社 取締役 AVシステム事業本部長の奥田隆司氏)とし,大型テレビ市場を今まで以上に積極的に攻略する構えである。今回の65インチ型品を含め,2005年度中に50インチ型超の液晶テレビを「PDPテレビに対抗できる価格」(同氏)で製品化する予定。

図1 世界最大65インチ型の液晶テレビが登場
シャープが展示した65インチ型の液晶テレビである。画面寸法は世界最大。画素数は1920×1080で,フルHDTVに対応する。輝度や消費電力は未公表である。2005年度中には量産を始める予定。
シャープは,約3年ぶりに「世界最大の液晶パネルを生産したメーカー」の称号を奪還したことになる。2001年秋に30インチ型を発表するころまで,同社は常に世界最大のパネルを発表してきたが,ここ最近は韓国勢に後塵を拝していた。65インチ型品の登場以前は,韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.の57インチ型が最大。韓国勢は,ガラス基板寸法が1100mm×1300mm前後の第5世代の液晶パネル工場を使って最大争いをしてきた。ただし,1枚のガラス基板から得られる画面寸法はほぼ限界に達し,ここ1年ほどは最大寸法が2インチほどしか拡大していない。シャープはいち早く立ち上げた1500mm×1800mmのガラス基板を使う第6世代工場を利用し,この停滞感を突き破った。
第6世代工場を使えば65インチ型を超える液晶パネルも実現可能だが,ガラス基板1枚から2枚得られる65インチ型品が最大とする。1枚のガラス基板から1枚の液晶パネルを得るのでは生産効率が低いというのが理由。数字だけの大画面競争は参加しない方針である。
LEDで一足飛びに100%超へ
液晶テレビでは,バックライト光源に発光ダイオード(LED)を使うことで色再現範囲を一気に拡大したソニーの「QUALIA 005」について,その色合いに関心が集まった。NTSC規格比105%で,従来の液晶テレビが70%台だったことと比べると,実に約1.5倍に拡大したことになる。同社は展示ブースの中心にこの液晶テレビを据え,並べて置いた従来の液晶テレビと比較しながら「赤色と緑色の『深み』が違う」と強調していた(図2(a))。
ソニーは,赤色(R),緑色(G),青色(B)の3種類のLEDを使った。LEDの発光色は原色に近く,光の3原色で白色光を構成できる。これまで光源に使ってきた冷陰極蛍光管(CCFL)に比べると,色の純度を落とすRGB以外の雑音光が極めて少ない。今回のバックライトを共同開発し,LEDを供給する米Lumileds Lighting,LLCによると,液晶パネルに使うカラー・フィルタの光学特性の関係で色再現範囲はNTSC規格比105%にとどまっているが,光源だけに限れば同135%にまで達するという。ソニーは新型AVパソコン「VAIO type X」にもLEDバックライト採用の液晶モニタを用意し,LEDの利点を強く印象付けていた(図2(b))。
(a)「QUALIA 005」の色の違いを強調 |
(b)「VAIO type X」向け液晶モニタ |
ソニーが来場者に対して強調したことは,新型液晶テレビ「QUALIA 005」の色再現範囲の広さである(a)。NTSC規格比105%と従来品比で約1.5倍。同社はこの液晶テレビと同等に色再現範囲を広げた液晶モニタも開発した(b)。「VAIO type X」向けに発売する。液晶テレビや液晶モニタ共に,赤色,緑色,青色の発光ダイオード(LED)をバックライトに使うことで色再現範囲を広げた。
QUALIA 005では,広い色再現範囲を使い切るため,ソニーは液晶/PDPテレビに利用する画像処理回路「ベガエンジンHD」の一部を変更した。階調表現を補正するLSIに専用品を使う。
もともと放送などで提供される通常の映像コンテンツは,ディスプレイの表現能力が色再現範囲70%程度であることを前提にしている。そのため,映像コンテンツの色再現範囲は実物よりもかなり狭い。ソニーは,色範囲が広い原画像を基にテレビ信号における物体の色の関係を洗い出し,元の色を再現するアルゴリズムを開発した。それを新開発のLSIに盛り込んだ。
LEDブームの予感
バックライトにLEDを使った液晶テレビは,今後各社から続々と製品化されそうである。それを裏付けるように,部品メーカーのブースが並ぶ展示ホールでは,LEDメーカーによるLEDバックライトの試作例が目白押しだった。2003年のCEATECでも試作例はあったものの,2004年はLEDバックライトが明るくなり,種類が増えるなど,本格的な実用期が近いことを印象付けた。
明るさが際立っていたのは,ロームが展示した15インチ型の液晶モニタである(図3(a))。画面輝度は800cd/m2と,一般的に500cd/m2程度の液晶テレビを大きく上回る。赤色LEDと青色LEDはそれぞれ34個,緑色LEDは68個使う。3種類のLEDがランダムな順番で1列に34個並んだLEDモジュールを液晶パネルの背面に4本配置した。LEDへの投入電力は,赤色LEDが約0.3W,緑色LEDと青色LEDはそれぞれ約0.6W~0.7W。これらからバックライト全体の消費電力は約70W~80Wと算出できる。個々のLEDは投入電力を1W程度にまで上げられ「画面をもっと明るくできる」(同社の説明員)という。
バックライト向けLEDモジュールの展示もあった。台湾Everlight Electronics Co.,Ltd.は,赤色LEDチップと青色LEDチップをそれぞれ6個,緑色LEDチップを5個の合計17個を1モジュールに搭載した製品を発表した。LEDを個別にバックライトに搭載する場合と比べ,実装の手間を省ける。2004年末までにサンプル出荷を始める。全チップを点灯させて白色光を得るときの光束は,投入電力7Wで最大126lmになる。
光源の種類については,豊田合成が白色LEDを使った32インチ型の液晶モニタを展示した(図3(b))。この白色LEDは紫外光を発するLEDチップと,紫外光をRGBそれぞれの波長の光に変換する蛍光体材料を組み合わせたもの。発光効率が高い上,色を混ぜ合わせる過程での光の損失が小さいため,RGB3種類のLEDを使う場合に比べて消費電力は低い。色再現範囲は未公表である。
(a)ロームの試作例 |
(b)豊田合成の試作例 |
ロームは,高出力の赤色,緑色,青色のLEDをバックライトに使った液晶モニタを展示した(a)。画面寸法は15インチ型。赤色LEDと青色LEDをそれぞれ34個,緑色LEDを68個使い,画面輝度800cd/m2を達成した。豊田合成は,白色LEDをバックライトに使った液晶モニタを試作した(b)。画面寸法は32インチ型と,ソニーの製品に次ぐ大きさ。1200個の白色LEDを搭載した。消費電力は約140Wである。画面輝度は未公表。
SEDは究極のテレビか

図4 暗所コントラスト比8600対1を誇るSEDテレビ
キヤノンと東芝は共同で,SEDパネルを紹介するブースを設けた。展示したパネルの画面寸法は36インチ型。画素数は1280×720。暗所コントラスト比は8600対1と極めて高い。
キヤノンと東芝が共同開発したSEDテレビは,暗所コントラスト比8600対1や,液晶の課題である動画の切れを強調した(図4)。展示ブース内には映画館のような暗い場所を設け,その中にSEDテレビと液晶テレビ,PDPテレビを据えて画質比較していた。
両社が展示したSEDテレビの画面寸法は36インチ型。2005年8月の量産時までに大型化を図り,50インチ型台を商品の中心に据える。50インチ型台品の画素ピッチは今回の試作品とほぼ同じで,フルHDTV対応になるという。輝度寿命については3万時間を目標に掲げ,量産時までの達成を目指している。SEDテレビは各画素に電子源を備え,ここから発する電子を蛍光体材料に当てて発光させる。この電子源をさらに工夫し,輝度寿命を延ばすという。
パネルや信号処理で10ms切る
液晶テレビで課題とされる動画像の「ボヤケ」を改善する技術の発表も目を引いた。液晶パネルや信号処理LSIを工夫し,応答時間数msを実現した。 OCB技術を適用した応答時間が5ms以下の液晶パネルを展示したのが東芝松下ディスプレイテクノロジー(TMD)である(図5(a))。同社はこれまでも同様のパネルを展示してきたが,今年は量産が始まり,かつ大画面化した。23インチ型品はナナオが2004年10月29日に発売する液晶テレビに搭載され,32インチ型は2005年春に量産が始まる。
OCB液晶は応答時間だけではなく,パネルの表示色数を増やすことにも有効という。液晶テレビ・メーカーの中には,RGB各色を現行の8ビットから10ビット以上の信号で表現する動きがある。10ビット化すると輝度の量子化ステップ幅は狭くなるので,1フレーム期間という限られた時間内に液晶の配向を精度よく制御することが必須。「OCBは高速に所望の配向に液晶を動かせる分,多階調化に有利」(TMDの説明員)と主張する。
信号処理LSIで高速化してきたのが日本ビクターである(図5(b))。信号処理技術を使った液晶パネルの高速応答化には,フレーム間の画像信号を比較して液晶を駆動する電圧を変調する「オーバー・ドライブ」が一般的だ。今回はこのオーバー・ドライブに,別の信号処理技術を加えたという。採用した信号処理の詳細は未公表と,当面はこの技術のブラック・ボックス化を狙う。
画像処理LSIと液晶パネルのドライバICの間に今回のLSIを設け,従来は同時間10ms~15ms程度の液晶テレビを,10msを大きく下回る程度に短縮できるという。ほとんどのメーカーの液晶パネルに使え,例えばOCB技術によるパネルもさらに高速化できるとする。
(a)東芝松下ディスプレイテクノロジーの液晶パネル |
(b)日本ビクターの技術紹介例 |
東芝松下ディスプレイテクノロジーは,液晶素子の応答時間が5ms以下と短い液晶パネルを展示した(a)。OCB技術で実現した。画面寸法と画素数は,32インチ型で1366×768,23インチ型で1280×768である。日本ビクターは信号処理LSIを使って液晶パネルの応答時間を短縮した例を公開した(b)。応答時間は未公表だが,従来はオーバー・ドライブ技術を使って10ms~15ms程度だった応答時間を下回るという。
数百万以上のパターンを用意
今のパネルやバックライトを前提に現行の液晶/PDPテレビの競いどころとして各社が力を入れて開発を進めるのが,画像処理技術である(図6)。今年のキーワードは「ヒストグラムの計測」だった。1フレームあるいは1フィールドごとに全画素の輝度ヒストグラムの計測結果からシーンに合ったガンマ曲線を選び出し,階調表現能力を高めようとするもの。例えば,明るい画像が多ければ明るい部分に多くの階調を割り振る。この際,画面がちらつかないように,一般的には前後のフィールドの輝度ヒストグラムも見て,補正の大きさを変える。
2003年までは松下電器産業が液晶テレビやPDPテレビにおいて,ヒストグラムを使った補正技術をうたってきた。2004年になって,日本ビクターや日立製作所,三洋電機,東芝などもヒストグラムの採用に踏み切った。
ガンマ曲線の変え方については,例えば日立製作所は,ガンマ曲線において階調の黒から白まで等間隔に設けた32点のそれぞれの値を変更する。変更量は輝度分布の偏りなどからあらかじめ決めた数式を使ってはじき出し,ガンマ曲線パターンを決める。
選択できるガンマ曲線の数をアピールするのが東芝である。1677万通りを用意した。「従来はガンマ曲線パターンを3つほど用意し,画面の平均輝度を基に選んでいた。それに比べ,今回は格段に画像が良くなった」(同社の説明員)。
(a)日立製作所のPDPテレビ |
(b)東芝の液晶テレビ |
(c)東芝のガンマ曲線例 |
|
日立製作所が発売した42インチ型PDPテレビである(a)。1フレームごとに,各画素の輝度のヒストグラムを計測し,ガンマ曲線を補正する技術を採用する。東芝も,同社の最新型液晶テレビにおいてこのような手法でガンマ曲線を補正する(b)。同社はあらかじめ1677万通りのガンマ曲線を用意しておき,輝度のヒストグラムに応じて最適なものを選び出す(c)。
リアプロも画質をアピール
液晶/PDPテレビの競争に,今回のCEATECでは背面投射型テレビ(リアプロ)も参入してきた。大画面の薄型テレビに対して「まだ値段が高くて…」と二の足を踏む消費者は少なくない。実際,普及の目安とされる「1インチ型当たり1万円未満の市販価格」を実現できている薄型テレビは,液晶テレビで32インチ型以下,PDPテレビでは43インチ型以下にとどまる(共にデジタル・チューナを備えた機種)。リアプロは従来からの大きさだけでなく画質でも価格対性能比を引き上げている。
ソニーと日本ビクターは70インチ型と画面サイズが特に大きい品種を出展した(図7)。ソニーは同品種を2005年1月に北米市場で発売予定。市販価格は約1万米ドルを見込む。奥行き方向の寸法は約60cmと厚いものの,65インチ型クラスのPDPモニタが200万円程度の希望小売価格を付けていることと比べて大幅に安い。フルHDTVにも対応している。肝心の画質も「展示品を見る限り非常にきれい」と一部ライバル・メーカーは評価していた。
日本ビクターは披露した70インチ型リアプロを「需要を探るために取りあえず試作した」(同社)と説明する。しかし,技術的な課題はクリアしたとしており,すぐにでも投入できることをうかがわせた。実際,光学系と表示素子は,同社が北米で販売中の製品(52インチ型品と61インチ型品)と同じである。同社は光学系を「当初から70インチ型品に利用することを見越して設計した」という。展示品の表示素子の画素数は1280×720だが,同社は前面投射型プロジェクタに向けて既にフルHDTV対応品を量産している。
(a)ソニーの70インチ型品と表示素子 |
(b)日本ビクターが試作した70インチ型品 |
ソニーと日本ビクターはそれぞれ70インチ型と大画面の背面投射型テレビ(リアプロ)を展示した。両社とも表示素子に自社が開発したLCOS(liquid crystal on silicon)素子を用いる。ソニーの表示素子はフルHDTVに対応する(a)。同社は展示品を2005年1月に北米において約1万米ドルで発売予定。日本ビクターは展示品の発売を現在のところ予定していない(b)。
台湾勢は価格攻勢をかける
今回のCEATECには台湾BenQ Corp.の日本法人ベンキュー ジャパンや,台湾Delta Electronics,Inc.グループのデルタ電子なども登場した。両社とも初出展で,テレビ受像機市場に対する強い意気込みを感じさせた。
ベンキュー ジャパンは2004年第4四半期に北米などで発売する46インチ型液晶テレビを披露した(図8)。同社は2005年に自社ブランド品で日本市場に参入する計画。日本で販売する製品や価格帯は未定だが,地上デジタル・テレビ放送対応機種も用意する方針だ。
デルタ電子は56インチ型リアプロや液晶テレビ,PDPテレビをずらりとブースに並べた(図9)。同社は製品を自社ブランドでなく,OEM供給として販売する方針だ。中でも注力するのがDMD素子を使ったリアプロ。このOEM供給元として「Delta社は2005年に世界シェアでトップに立つことが目標」(デルタ電子)という。フルHDTV対応品も2005年第1四半期から量産を始め,価格帯は「日本メーカーの自社生産品より確実に安い水準」(同社)とする。
 図8 台湾メーカーの日本参入が加速 台湾BenQ Corp.の日本法人ベンキュー ジャパンは,46インチ型液晶テレビを展示した。展示品はBenQ社が北米や欧州などで2004年10月~12月に発売する予定。同社が自社ブランド品で日本市場へ参入するのは2005年中という。 |
 図9 台湾勢もリアプロに注力 台湾Delta Electronics,Inc.の日本法人であるデルタ電子は,56インチ型の背面投射型テレビ(リアプロ)を披露した。Delta社のOEM供給先が北米で販売中の製品を基に,外観を変えている。本体の奥行きは48cm。表示素子にDMD素子を1つ使う。 |
新しい駆動方式の登場でスピーカは○から□へ
映像の出力装置であるディスプレイの薄型化・大型化は,音声の出力装置にも変化を及ぼしている。CEATECでは,四角いスピーカの展示が目立った(図A-1)。従来の円すい状の振動板から四角い振動板へと変更できたのは,新しい駆動方式の登場にある。
TDKが展示したスピーカは,磁界を変化させると最大で1100ppmほど伸縮する「超磁歪素子」で駆動する。この超磁歪素子をスピーカのエキサイタに用いて,64cm×14cm×1cmの四角いアクリル板から音楽を流すデモを見せた。超磁歪素子の周囲に巻いたコイルに流す電流を変えて磁界を変化させる。今後は,超磁歪素子の伸縮を大きくすることで,苦手な低音領域の出力も目指す。
TDKよりも大きい100cm×40cmの巨大なスピーカを厚さ約2cmで実現したのは,東芝と早稲田大学のグループである。Alを蒸着した厚さ3μmの樹脂フィルムを振動板とする。この振動板を導電材料を塗布した布で挟み込んでスピーカとした。布は電極として働き,東芝のパワー半導体素子で0Vと1000Vを高速に切り替えて振動板を動かす。スピーカには「高電圧注意」の文字があったため,来場者は恐る恐る近づいていた。
(a)TDKの「超磁歪スピーカ」 |
(b)東芝と早稲田大学の「コンデンサスピーカ」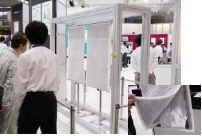 |
TDKは,磁界の変化で伸び縮みする「超磁歪素子」を用いた薄型スピーカを展示した(a)。厚さが1cmの透明なアクリル板を振動板とする。超磁歪素子スピーカの出力周波数範囲は900Hz~18kHzと高音域が中心のため,220Hz~900Hz用と220Hz以下用の2種類のスピーカを追加して補っている。製品化時期は2005年6月ごろ。価格はアンプとスピーカを含めて5万円以下を目指している。東芝と早稲田大学は,大きさが100cm×40cmと巨大な薄型スピーカを展示した(b)。平面のほか,丸めて円筒型のスピーカにもできるという。