失敗したと決めつけてはいけないのかもしれないが、幾つかの自動車メーカーは慣れ親しんだ「プラットフォーム」と決別しようとしている。日産自動車や独Volkswagen社は明確に「脱プラットフォーム」をうたい、トヨタ自動車やマツダも同様の方向にかじを切った。
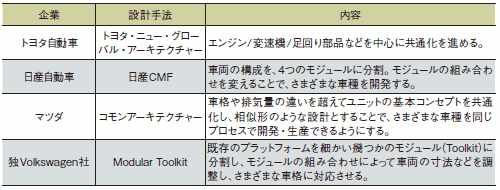
自動車のプラットフォームは、主に同一セグメントの車種で共有することを想定した部品の集合体だが、結局は思ったように共有できなかったことを日産自動車やVolkswagen社は認めている。今後、両社は車両を「モジュール」という細かい単位に分割し、セグメントの枠組みを超えてモジュール単位で共通化を進めていくことになる。
プラットフォームは“大きすぎた”
なぜ、プラットフォームをうまく共有できなかったのか。その答えは、日産自動車が新たに採り入れる車両設計手法「日産CMF」に見いだせる。日産CMFでは車両の構成を大きく4つのモジュール(これと別に電子部品に関するアーキテクチャが存在する)に分割しているが、このモジュールがどのように決まったかというと、車両に求められる機能や性能が基になっている。それぞれのモジュールに割り当てた機能や性能を、同社はバリエーション因子と呼んでいる。
例えば車両後方のリア・アンダーボディというモジュールには動性能(走行性能)というバリエーション因子が割り当てられている。これは、走行性能に関してはほとんどリア・アンダーボディで決めてしまうことを意味している。裏を返せば、それ以外のモジュールでは基本的に走行性能を考慮せずに済むのだ(詳細は『日経ものづくり』2012年4月号を参照)。
プラットフォームは、そのあまりの大きさ(物理的にも概念的にも)故、さまざまな機能や性能と密接にかかわってくる。従って、車種ごとに異なる機能や性能の要求に応じて、プラットフォームも調整しなければならなかった。ありとあらゆる要素を詰め込んでいたことが、プラットフォームの共有化が難しかった原因である。自動車は「擦り合わせ」の代表格ともいわれてきたが、それは物理的な構造と機能・性能の複雑な関係性に起因していたといえる。
プラットフォームをモジュールに分割したところで、機能や性能との関係が複雑に絡み合ったままでは、本質的な解決にはならない。その点を日産自動車は十分に認識しており、単に物理的に分割しただけではなく、モジュールにひも付く機能や性能に関しても物理的な構造と一緒に分割できているという。そんなきれいに割り切れるものなのかという疑問はあるが、電子化の進展によってそうしたことがやりやすくなっている面はあるだろう。今後、物理的な部品の種類数を増やさずに機能や性能のバリエーションを充実させる必要があり、前出の電子アーキテクチャーが重要なカギを握る。
それでは、モジュール化の進展によって自動車は「擦り合わせ」製品ではなくなるのか。個別車種の設計という意味では「組み合わせ」製品としての性格が強まるだろう。だが、車両をどのようなモジュールに分割するのかというアーキテクチャーの設計は、完全な擦り合わせである。日本の企業が得意とする擦り合わせの能力はアーキテクチャーの設計で生かすべきであり、日本の技術者が手掛ける仕事も個別製品の設計からアーキテクチャーの設計へと徐々に移行するだろう。



















































