自分が初めてかかわった製品が無事発売となり,以降のプロジェクトでも積極的に開発に携わってきた樋口くん。そこに知的財産部のクミさんから内線電話が掛かってきました。なんと,自分の発明の出願は拒絶されてしまったとのこと。ところが,クミさんは「そんなの普通だから,落ち込まないでね」という感じで,特に残念そうな雰囲気はありません。実験やら実施例やらあれだけ準備して出願したのに,何がまずかったのか,樋口くんにはさっぱり分かりません。そもそも拒絶されるのは「普通」なことなの?
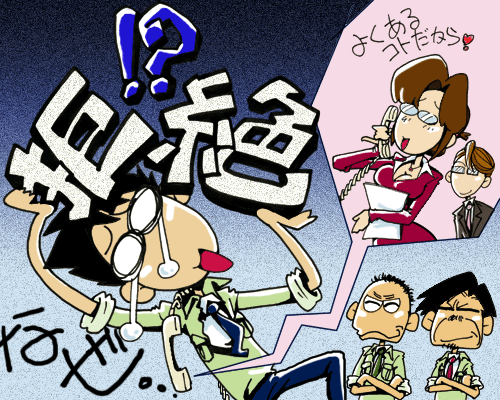
出願経験が豊富な人には当たり前なことですが,一般に出願審査請求を行った出願のほとんどは拒絶されます。とはいえ,「拒絶=権利化できない」ということではありません。むしろ,ここからが「本番」といえるかもしれません。
「拒絶理由通知」が送られてくる
まずは,「拒絶≠権利化できない」について説明します。出願審査請求を行った発明のうち,新規性がないもの,進歩性がないもの,記載用件を満たしていないものなどは,拒絶されます。ただし,拒絶されたら直ちに権利化への道が閉ざされるわけではありません。その場合は「こういう理由でこのままでは特許にするわけにはいきませんよ」という内容が書かれた通知(拒絶理由通知)が特許庁から出願人に送られてきます。出願人は,その拒絶理由通知に対して「いいえ,そんなことはありません」と反論・主張する機会が与えられます。
例えば,権利範囲が広すぎて公知技術との差異がないものまで含んでいたような場合,権利範囲を狭めることによって,引用された公知技術との差異が明確になるような補正を行うなどの対応を採ります。こうしたやり取り(1回の場合もあれば,複数回の場合もある)を経た後,拒絶理由が解消されると,晴れて「特許査定」となり,権利化が認められます。一方,上述のやり取りを経ても拒絶理由が解消されない場合は,「拒絶査定」となります。一定期間が経過して拒絶査定が確定した場合,権利化への道が閉ざされます。
初めから狭すぎたのかも…
次に,「拒絶されるのは普通」と考えてもよいということについて説明します。このことは,逆に拒絶理由通知を受けることなく一発で特許査定がもらえた場合を考えると,よく分かります。
そうしたケースでは,特許庁の審査官への反論が不要になり短時間で特許が取れる上,自分の発明が何ら疑問の余地なく認められたという良い印象を受けるかもしれません。しかし,必ずしもそれが最善とは言い切れないのです。当連載で繰り返し説明してきましたが,一般に特許請求の範囲は将来の実施や他社の侵害を考慮して少し広めに書いておくものです。そして,拒絶理由通知で引用された従来技術や審査官の認定に応じ,拒絶理由を解消するために必要最低限の「範囲の限定」を行うことによって,取得し得る最も広い権利範囲を目指します。こうした観点から考えると,一発で特許査定を得たということは,上述のやり取りを経ていないので,初めから権利範囲を狭くしすぎていた恐れがあるわけです*。
拒絶を恐れて自ら権利範囲を狭めてしまっては,本末転倒です。多くの場合は,拒絶されることもある程度覚悟の上で最大の権利範囲を目指して出願します。だからこそ,今回のケースでは樋口くんは落ち込むことなく「拒絶されるのは普通」と考えてもよいということになるわけです。もちろん,最も権利を取得したい部分に対してかなり近い公知技術が引用された場合などは,さすがに悠然と構えているわけにはいきません。しかし,今回のクミさんのように知財部の担当者がそれほど問題視していないケースでは,権利範囲を多少狭めれば拒絶理由を解消できる可能性が高いと考えてよさそうです。
本当に欲しい権利は何か
出願が拒絶された場合に,発明者がすべきことがあります。それは,権利範囲のうち重要な部分とそうでない部分を明確にしておくことです。知財部や弁理士に対応を任せる際は,そのことを早い段階で伝えておくとよいでしょう。
例えば,拒絶された特許請求の範囲には実施例A,B,Cが記載されており,そのうちAは絶対に権利を取りたい範囲,Bはできれば権利を取りたい範囲,Cは権利を取れなくてもそれほど問題ないような範囲であるとします。このような方針が明確になっていれば,「では,Cはあきらめて重要なA,Bを確実に取りにいこう」とか「B,Cは取れそうだけど,Aは厳しそう。でも,Aが重要だからダメモトで食い下がろう」という対応を決めやすくなります。
拒絶理由を解消するための補正を行う上で注意すべき点としては,出願当初の明細書等に記載されていない事項(これを新規事項といいます)は追加できないということです。新規事項の追加が禁止されている理由は簡単で,このような補正を認めてしまうと,出願時に開示されていない技術的事項に対して特許権を付与してしまうことになり,「発明開示代償保護」という特許法の趣旨に反してしまうからです。従って,出願の段階であらかじめ将来の補正の可能性に配慮しておく必要があります。例えば「出願の段階では広い権利範囲でチャレンジするけど,拒絶されたときは権利範囲を狭めて,せめて製品の具体的構成については権利を取りたい。将来補正を行えるように,発明提案書における具体的構成についての説明をもう少し充実させておこう」というように,一歩踏み込んで考えられるようになれば,意図通りの権利を取得できる可能性が高まるでしょう。
連載の最後に…
連載はひとまずこれで終了となりますが,最後に筆者から技術者の皆さんにメッセージがあります。皆さんが生み出した発明は,皆さまの財産であり功績でもあります。特許とは,それを目に見える形にしたものといえます。連載でいろいろと書いてきましたが,まずはご自身の発明を積極的に出願してみてください。そうした過程で分かってくることも多いと思います。またどこかでお会いしましょう。



















































