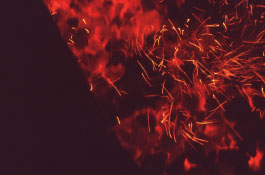
「奥底に秘められた美しさとでも言うんやろうか。名刀と呼ばれる作品にはそれがあると思う。例えば正宗(まさむね)なんかは、見るたびに変わりよる。はたちのとき見たのと、50歳で見たのと、まるで印象が違うんやからな」
名刀の代名詞にもなっている正宗の作品に託して日本刀の持つ深みを表現する河内には、二人の師がいた。大学卒業後すぐに入門した宮入昭平(みやいりあきひら:後に行平[ゆきひら]に改名)、その宮入から独立した後、再入門した隅谷正峯(すみたにまさみね)である。いずれもが、現在まで6人しか認定されていない人間国宝の指定を受けた名匠である。その二人に学んだ河内もまた、日本美術刀剣保存協会で「新作刀展無鑑査」という、現代刀匠として最上級の評価を得る名匠として知られる存在である。

現在67歳。もちろん現役である。奈良の東吉野に居を構え、弟子たちを指導しつつ新たな作品を世に問い続けている。
その彼が日本刀の素材として用意した玉鋼のざらざらとした肌合いの黒い塊を見ると、それが精緻で透明感のある日本刀になるとはにわかには信じがたい。無骨な塊の組成は均一ではなく、炭素量の異なる部分が混ざり合っており、さらには多くの不純物を含む部分がある。水減しから始まるいくつかの工程で、不純物が多い部分は除き、炭素量の多い部分と少ない部分を細かく選別、分類するのである。
まずは、適度な温度にまで火床(ほど)で赤めて、薄く煎餅状に叩きのばす水減しを行なう。さらに次の小割り仕事で、薄く延ばした玉鋼を鉄敷(かなしき)の上で細かく割っていく。ぱし、と気持ちよく割れる時もあれば、湿った煎餅のように、ぐにゃりと曲がり何度か叩いてようやく割れるものもある。割れ口は、いずれも銀色ににぶく光っている。

その細かく割った破片を河内は一つずつ見分け、分類していく。素人にはどれも同じに見えてしまう破片だが、刀匠たちは、小割りをする際の割れ方、割れ口の組織を見るだけで、炭素や鉄滓(てっさい:スラグ、不純物)の多寡を一瞬にして判別してしまうのだ。
「ほら、よく見るとわかるでしょ。こんな風に結晶になっているところは炭素が多すぎる。一番いいのはここらへんですよ、粒子が細かくて」
そう説明しながらも河内の手は止まらない。小割りにした玉鋼の割れ口をちらりと見ながら、それぞれの等級に応じて決められた缶の中へ放り込む。これら小片の組み合わせ方で地鉄(じがね)の出来上がりが大きく左右される。なんとも無造作にみえるが、玉鋼の炭素量を読み抜く刀匠の「目」の良さがものを言う大切な工程だ。



















































