
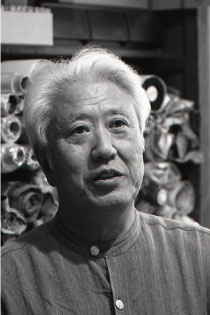
ひとつの茶入が土田友湖のもとに届けられた。室町時代に作られた瀬戸焼の品で、銘が「霜夜(しもよ)」とある。この銘は小堀遠州の息子、小堀十左衛門が命名者だという。ねっとりとしたこげ茶色の肌に、淡い色の模様がふつふつと入っている様子は、なるほど、霜の降りた静謐な夜を思わせる。
友湖の工房では一見の客は受けない。道具屋か、もしくは出入りのある人を介しての仕事が通常だ。たとえば茶をたしなむ人の間では「仕服といえば友湖」というほど、その名は知れわたっている。それは、初級者が稽古で「拝見」の練習をするときなどに、「お仕服は?」「友湖でございます」という架空の問答が定番になっていることからも、うかがい知れる。だが実際に友湖作の仕服を見たことがある、という人はきわめて稀なことも事実だ。友湖の仕服とは、いわば閉ざされた世界で流通する伝説の品なのである。
が、当人や土田家が閉鎖的かといえば、そんなことはまったくない。あくまでも淡々と自分の仕事を守る、という空気が流れているだけである。


「私らの仕事はお預かりして、では5日後に、というものではありません。そのお茶入にふさわしい仕服をしつらえるのに、中には1年ほどお預かりすることもあります。ですので、お互いの信用がとても大切になるのです」
友湖がいちばんに考えているのは「ブランド力」ではない。人間関係の中から生まれる「お互いの信用」なのである。
だからなのか、仕服の制作には納期という概念はない。
「すっと行くときと、そうでないときと、毎回それぞれ違いますので、何日までにヨーイドン、というのでは仕事にならないのです」
どれほど熟練の技を磨いても、制作の第1歩はいつも不確定だ。そもそも茶入という存在がそれだけ大きい、ということでもある。そこでまずは茶入を自分の傍に置く時間が必要となる。
仕服を構成する部品は、それほど複雑ではない。袋となる裂(きれ)本体と、その上にかける「緒(お)」。「緒」を裂につなぐ「つがり」と、大きく分けて3部品である。目の前にある茶入に、どんな裂を選び、選んだ裂にどのような色の緒を合わせるか。茶入の形だけでなく、その由緒も含めて袋師はイメージを膨らませていく。

今回の「霜夜」もそうであるが、友湖のもとに持ちこまれる茶入は、300年もしくは500年という、とんでもなく重い年月を経てきたものが多い。そのような茶入は、代々の持ち主が歴史上の人物であることも多く、すでに由緒をたっぷり含んだ仕服が付いていることも常だ。なので、自分が新たに「着せ替え」の仕服を作る場合は、すでにあるものとのバランスも考慮に入れる。




















































